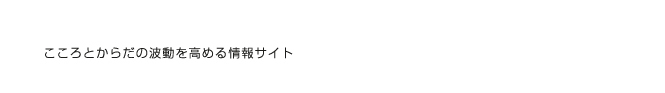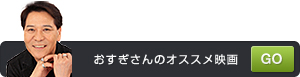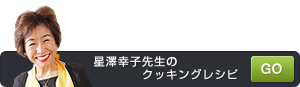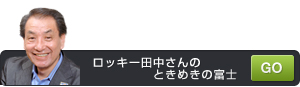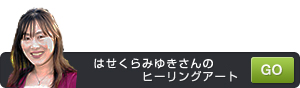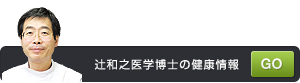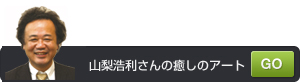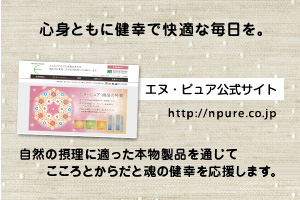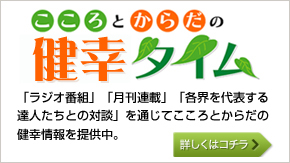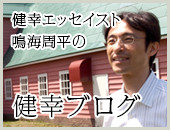【vol.87】辻和之先生の健康コーナー|「わかりやすい東洋医学講座」 第37回 東洋医学の基礎理論36 肺と腎
東洋医学の基礎理論36
肺と腎
【肺と腎の正常な関係】
肺と腎は、1)津液代謝、2)呼吸運動において深く関わっています。
⑴津液代謝
肺は水の上源と云われ、粛降作用と通調水道(津液の循環と調節)の機能により水液を腎まで運び、水を主る腎は、腎に運ばれた水液を清濁に分別し、体内に必要な清の部分は、尿細管を経て体内に再吸収され、肺まで運ばれます。再吸収されなかった濁の部分は、気化されて膀胱に送られ、尿として排出されます。
⑵呼吸
肺は、呼吸を主り、粛降作用によって気を降ろし、呼気を助けます。腎は、納気を主り、気を納めることで、吸気を助けます。肺の粛降作用は、腎の納気作用を補助し、腎の納気作用は、肺の粛降作用の維持に役立っています。
【肺と腎の病的状態】
肺は、呼気を主るので、肺の機能に異常があると呼気性の呼吸困難が呈しやすくなります。(例:気管支喘息)このような場合、肺の宣散粛降機能を回復させる必要があります。治療の際に宣散を回復させる麻黄や粛降を改善させる杏仁が用いられます。代表的な処方として、麻杏甘石湯、神秘湯などがあります。
一方腎は、納気を主るので、腎の機能に異常があると吸気性の呼吸困難を呈しやすくなります。このような場合、腎の機能を補助する必要があります。代表的な処方に都気丸(六味丸+五味子)、麦味地黄丸(六味丸+五味子+麦門冬)があります。腎を補助する六味丸に、上逆した肺気を納めて止咳する五味子、肺陰を滋養する麦門冬が配合されています。
*肺腎陰虚証:肺と腎には、津液代謝により相互に陰液を生み出す関係にあります。肉体疲労、房事過多、慢性病が原因で腎陰虚を呈することに端を発し、腎陰が不足して肺を滋養出来ず肺陰虚を生じます。肺陰虚により腎陰を滋養出来ず、腎陰虚を増長します。腎陰虚や肺陰虚により両者の不足(肺腎陰虚)に陥り易くなります。
肺腎陰虚症状:空咳、嗄声、盗汗(寝汗)、両頬部の紅潮、骨蒸潮熱(体内から蒸されるような発熱)などの症状を呈します。治療は、滋陰降火湯、麦味地黄丸などを用います。
*肺腎気虚証:腎の納気機能低下に腎陽虚と肺気虚が合併して肺内に水湿が停滞した病態で腎陽虚(腎陽が不足、下肢冷感、尿失禁、顔が蒼白いなどの症状を呈する)により肺気虚を呈し、肺気の不足により肺の宣発・粛降作用が低下して腎を始め全身に津液を配ることが出来ず、肺内に水液が貯留した状態になり、多量の白色痰を伴う咳嗽と呼吸困難を生じます。肺気虚が長引けば、腎の納気作用が低下して息切れを生じます。症状:白色の多量の痰を伴う咳嗽、自汗、浮腫を呈します。治療:八味地黄丸に苓甘姜味辛夏仁湯、小青竜湯などを用います。
プロフィール
医療法人和漢全人会花月クリニック
日本東洋医学会専門医
医学博士 辻 和之
昭和26年 北海道江差町に生まれる
昭和50年 千葉大学薬学部卒業
昭和57年 旭川医科大学卒業
平成 4年 医学博士取得
平成10年 新十津川で医療法人和漢全人会花月クリニック開設
日本東洋医学会 専門医
日本糖尿病学会 専門医
日本内科学会 認定医
日本内視鏡学会 認定医