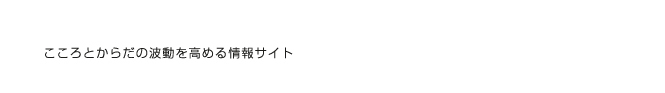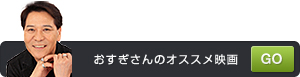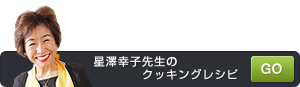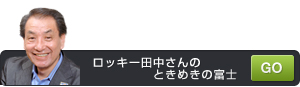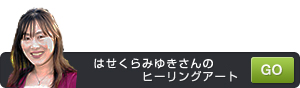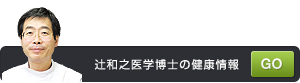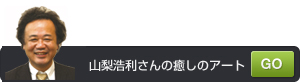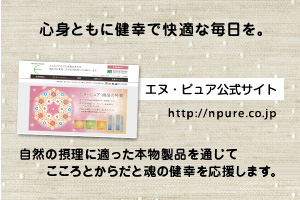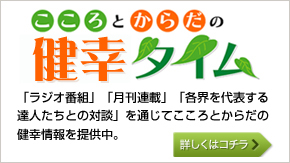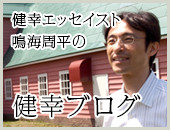【vol.45】こころとからだの健康タイム|ゲスト 帯津 良一 先生~前編~
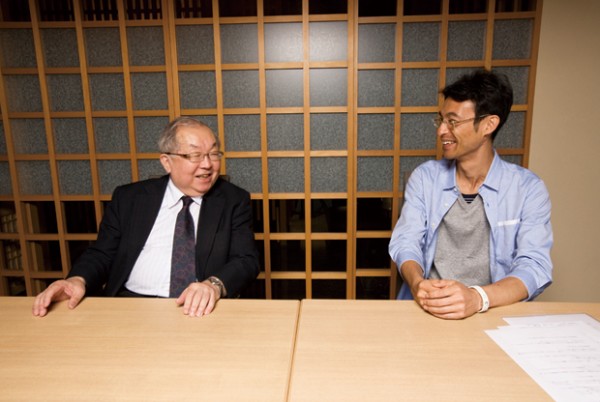
人間をまるごと診るホリスティック医学の第一人者である帯津三敬病院名誉院長の帯津良一先生。日々の診察の傍ら、全国をまわって氣功の指導や講演などを行い、現在までの著書数は240冊以上にもおよびます。
この度、エヌ・ピュア代表である鳴海周平の著作「健康の基本~心と体を健康にするカンタン習慣63~」の監修をご快諾いただいたご縁から、同著の対談ページを前編と後編に分けて、特別版として紹介いたします。
(「健康の基本 ~心と体を健康にするカンタン習慣63~(ワニ・プラス)」対談ページより抜粋して紹介します)
人間をまるごと診るホリスティック医学
鳴海周平(以下 鳴海)
帯津先生とは、2004年に弊社会報誌の対談でご一緒させていただいて以来、8年ぶりの対談ということになります。
帯津良一(以下 帯津)
もう8年になりますか。早いものですね。鳴海さんとは当時からとても近い健康観を持った同志という認識でおりましたから、今回もこうして語り合えることを楽しみにしていました。
鳴海 たいへん光栄なお言葉をいただき、ありがとうございます。
私は帯津先生の「人間をまるごと診るホリスティック医学」という考え方が大好きで、いつも参考にさせていただいています。
帯津 英語で書かれた本を見ると「ホリスティック医学とは、ボディ、マインド、スピリット」と書いてあります。つまり、からだ、こころ、そしていのち。
いのちは魂と言い換えてもいいでしょう。
このすべてをまるごと捉える医学が、私が追い求めている「ホリスティック医学」です。
鳴海 帯津先生が西洋医学と中国医学の統合だけに留まらず、インドのアーユルヴェーダやホメオパシー、スピリチュアルヒーリングなどにも治療法の幅を広げていらっしゃるのは、「人間をまるごと診る」という大きな視点があるからなんですね。
帯津 私は、ホリスティック医学には「場」という考え方がとても重要だと思っているんです。
からだの中は、いのちに関わる物理量が「いのちの場」をつくっています。このエネルギーがいのちです。そして、なんらかの理由でこのエネルギーが低下した時に、これを回復させようとする、「場」自身に備わっている能力が「自然治癒力」ではないかと思うんですね。
こうした「場」の回復作業を外部からの働きでおこなうことが、医療などによる「治し」や「癒し」。自分の意志でおこなうことを「養生」と考えるとわかりやすいのではないでしょうか。
そして「場」の自然治癒力は人間だけに備わっているのではなく、ありとあらゆる「場」にそうした働きがある。だから、いい「場」に身を置くことでも、癒しの効果を実感できるんです。
鳴海 作家の五木寛之さんは「18歳の時に身体検査を受けたきり、病院に行ったことがない」とおっしゃっていますが、その理由は、病院という「場」の氣がよくないからだそうです。行くと病気になってしまいそうな氣がすると(笑)。
帯津先生はそうした面にもとても配慮されていて、2009年に新築した病院はいい「場」をつくることに徹底してこだわっていらっしゃる。
私も先日お伺いしましたが、本当に素晴らしい「場」ですね。特に130畳もあるという氣功の道場には驚きました。こうしたいい「場」に身を置くことができると、患者さんの回復にもとても良い効果が期待できそうです。
帯津 新しい病院は、今までの集大成と言ってもいいと思います。廊下も広くて、とても居心地がいいですし、99室ある病室はすべて個室です。道場ではひっきりなしに氣功や太極拳、呼吸法などのプログラムが組まれていますから、常にいい「場」が形成されています。患者さんは、病院に体調を良くしたくていらっしゃるわけですから、ほんらいは病院こそがエネルギーの高い「場」でなければなりません。そこにいるだけでも癒されていくような「場」が理想ですね。
鳴海 帯津先生の病院だと、五木さんも安心して来られそうです(笑)。
帯津 ただ、行き着くところは、やはり職員ひとりひとりの意識なんですよ。
自分のいのちのエネルギーと患者さんの
いのちのエネルギーを、日々少しずつでも高め続けていこうとする志と覚悟が必要なんです。「今日より良い明日を」という当院の基本理念は、こうした志と覚悟を表しています。
患者さんは、からだだけでなく、こころやいのちにも目を向けて欲しいと思っていますから、このすべてを丸ごと捉えようとするホリスティックな考え方は今後ますます重要になってくるでしょう。
鳴海 エビデンス(科学的な根拠)ばかりを重視する既存の西洋医学では、こころやいのちの問題まで捉えることはちょっと難しいかもしれませんね。
本書「健康の基本」でも触れましたが、本当に大切なものは、数値やデータでは表しきれない、目に見えにくいことの中に在るように思います。
帯津 おっしゃるとおりですね。西洋医学は科学的なエビデンスを重要視しますが、長い歴史のある伝統的な民間療法などには、時間の長さという目に見えない立派なエビデンスがあると考えていいと思うんです。
五木寛之さんは「養生の実技」(角川書店・2004年)という本の中で「科学的な裏付けをしようとすると、民間療法にとっていちばんいいものが失われる」ということをおっしゃっていますが、私もそのとおりだと思うんですね。先人たちから長い年月をかけて受け継がれてきた経験則は、科学的な裏付けだけで判断できるものではありません。要は、患者さんの状態が少しでも良くなればいい。
理論や理屈で病気を捉えるよりも、先ずは「患者さんのために何ができるのか」というところから考えていく必要があると思うんです。初めに数値ありき、ではなく、先ずは患者さんと医者のつながり、信頼感がちゃんと保たれていることが大切ですよ。
医学界は「統合」の流れへ向かっている
帯津 数値と言えば、メタボリックシンドロームの目安というのもありますが、あれは余計なお世話ですね(笑)。健康はいのちのエネルギーの高さですから、検査の数値だけでは表せないんです。現に、最初に設定された最高血圧やコレステロールなどの基準数値が数年の間に下げられた結果、その間の人たちは、みんな薬の対象になってしまったわけです。要は、健康のハードルをどこに設定するかということなんですが、今のように数値だけを全面に出して検査を勧めている状況は、ただ不安感を煽っているように感じてしまいます。
鳴海 人間が生まれながらに備えているホメオスタシス(恒常性)の働きから考えても、常に動きのあるいのちに対して、ある瞬間の数値だけで健康状態を判断してしまうのは、たしかにおかしいですよね。ましてや、その薬がなかなか途中で止められないとなると、たいへん大きな問題だと思います。
目に見える数値だけに依存し過ぎることは、かえってもともと持っている生命力を弱めてしまうような氣がしますね。
帯津 科学的にまだよくわかっていない「いのち」の問題に対して、わかったことだけで対応しようとすることにそもそも無理があるんですよ。
患者さんと向き合っていると「理詰めでは、たしかにこの療法なんだけど、感覚としてはこっちの薬がいいんじゃないか」と閃くことがあって、結果的にその閃きのほうが正しかったりするわけです。だから、エビデンスも大事だけど、そこに閃き(直感)を統合することも大事なんです。
患者さんの立場になってみると、とにかく今の辛い状態が良くなればいいわけですから、エビデンスは乏しくても一筋の光明が見えるような治療法があれば、選択肢はたくさんあった方がいい。こうした観点から捉えても、医学界はこれから「統合」という大きな流れに向かっていくように思います。
西洋医学が得意とする「部分」と東洋医学が得意とする「全体」。
薬や手術のような「治し」といのちのエネルギーを高める「癒し」。
症状を治す「治療医学」と事前にそれを防ぐための「予防医学」。
医者がやってくれる「医療」と自分でおこなうことのできる「養生」。
こうした要素をひとつひとつ大事にしながら、積分して新しいものを創り上げていくことが、これからの医学には必要だと思います。
そしてその先に「生」と「死」を統合したホリスティック医学がある。
本書で鳴海さんが紹介している健康の秘訣は、予防医学や癒しの根幹ともなる養生法ですから、皆さんおおいに実践して、来るべきホリスティックな時代の先駆けとなっていただきたいですね。
「生」と「死」を統合する生き方
鳴海 終末期医療の専門家でもある緩和医療医の大津秀一先生は、ご自身の著書「死ぬ時に後悔すること25」(致知出版社・2009年)の中で、「生と死の壁を乗り越えられなかったこと」を挙げています。仕事柄、たくさんの方の最後を看取っているわけですが、自分なりの死生観を持っている人は、終末期になって死に直面してもじつに堂々としているそうです。
本書の中でも「人間は必ず死ぬものです。それならば「幸せな死」を迎えることこそ、人間の究極の目標なのではないか」という、医師の川嶋朗先生(東京女子医科大学付属青山自然医療研究所クリニック所長)の言葉を紹介していますが、からだ、こころ、いのちという大きな観点から健康というものを捉えた時に、「死」についても思いを巡らせておく必要があるのではないでしょうか。
帯津 まさにおっしゃるとおりで、ホリスティック医学が目指す最終的な課題は「生」と「死」の統合なんです。
アメリカのホリスティック医学のリーダー的存在でもあるディーパック・チョプラ博士も「本当の健康のためには、死についての問題をしっかり考えて、その恐怖から解放される必要がある」と述べているように、その人なりの死生観を養っておくことはとても大切なことだと思います。生まれてきたからには必ず死ぬわけですからね。
私は、良い「生き様」というのがあるように、良い「死に様」というのがあってもいいんじゃないかと思うんです。
身近な人で言うと、太極拳の楊名時先生は、見事に生と死の統合を果たされた方でした。
先生とは飲み仲間でもありましたから、大病で手術をされた後も、月に2、3回は先生のお宅に伺って、2人で飲み交わすことが6、7年続いていました。ある時期から「私は生きるも死ぬもあるがままだから、主治医としてよろしく頼みますよ」とおっしゃるようになりました。「死ぬ時は、あなたの病院で死にますから、よろしく」と言うわけです。
その後、先生は予告どおり私のところで入院して最後を迎えられたわけですが、検査も治療もやりたがらずに「あるがまま」を貫かれました。
亡くなる時も、もうほとんど意識がないのに、私が顔を近づけて呼んだらパッと目を開いて右手を出してきたんです。それが凄い力で、とても死期が迫っている人とは思えないほど力強い握手でした。それから左手でも握手をして、お互い睨めっこをしました。その後は、集まってきたご家族やお孫さんたちとひとりひとり握手をしながらひと言ずつ話をして、全員と握手をし終わってからすぐに心臓が止まったんです。これは凄いな、と思いましたね。生と死を統合するとは、こういうことだと。
人生の中で、楊名時先生のような方と出会えたことは、私にとってかけがえないのない宝物ですね。
鳴海 生と死が統合されると、そんなに素晴らしい旅立ちができるんですね。
先日、新聞の連載で脚本家の倉本聰さんがエッセイを掲載されていまして、その中で御父様が亡くなった時のことを書かれていたんです。
当時、倉本さんは高校生だったそうですが、御父様が狭心症の発作で危ない状態だった時に、「みんなで賛美歌を歌おうよ」と言って、歌い終わったとたんに天井の一点を見ながら「きたきた」と笑って亡くなったというエピソードを紹介されていました。
「何かが迎えにきた印象がして、何かに立ち向かうような力強さも感じた」と倉本さんはおっしゃっていますが、こうした旅立ちの姿も生と死を統合しているように思います。
帯津 ほーう、そのお話も素晴らしいですね。やはり、生と死が統合されると、死に対する恐怖感のようなものがなくなるのでしょう。まさに理想的な死に様です。
ヘルマン・ヘッセの詩に
よろこんで朽ち果て
万有の中に崩壊していく
というのがありますが、まさにこの境地ですね。
ここで言う「万有」とは「あの世」のことであると私は考えているんです。魂の故郷である「虚空」ですね。
死に逝く人の傍らで見送りをすると、みなさん一様に安堵の表情を浮かべて旅立ちますが、これは「故郷」に帰っていく表情なんだなぁ、と思うと納得がいきます。
鳴海 哲学者の池田晶子さんが「人生のほんとう」(トランスビュー・2006年)という本の中で「池田某は確実に死にます。みなさんもそうです。確実に死にますが、しかし死ぬという言葉すら超えた存在というものに気が付いて、池田は死ぬが私は死なないと、そういう変な言い方が出てきたりします」と書いています。
自分の中に流れている永遠性のある存在、これは魂とも言ってもよいと思いますが、そういったものの存在までを視野に入れて考えると、日頃おこなう養生にもずいぶんと奥行きが感じられてきますね。
帯津 「養生」とは、いのち(魂)を正しく養うこと、いのちを養いながら生きていくことです。
五木寛之さんは「養生の実技」(角川書店)の中で「明日死ぬとわかってもするのが養生である」とおっしゃっていますが、まさにそのとおりで、長生きとか、病気を克服するためだけにやるのではなく、死ぬ直前まで「いのちのエネルギー」を高め続けていくのが「養生」なんですね。
さらに言えば、死んだ後の世界でも、そのまま「いのちのエネルギー」を高め続けていく、というところまで視野に入れた方がいい。
これが私の考えている「養生」であり、生と死を統合したホリスティックな生き方です。
対談の続きは、次号掲載の後編で紹介します。
どうぞ楽しみにお待ちください。